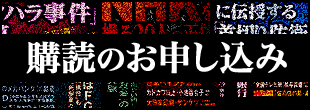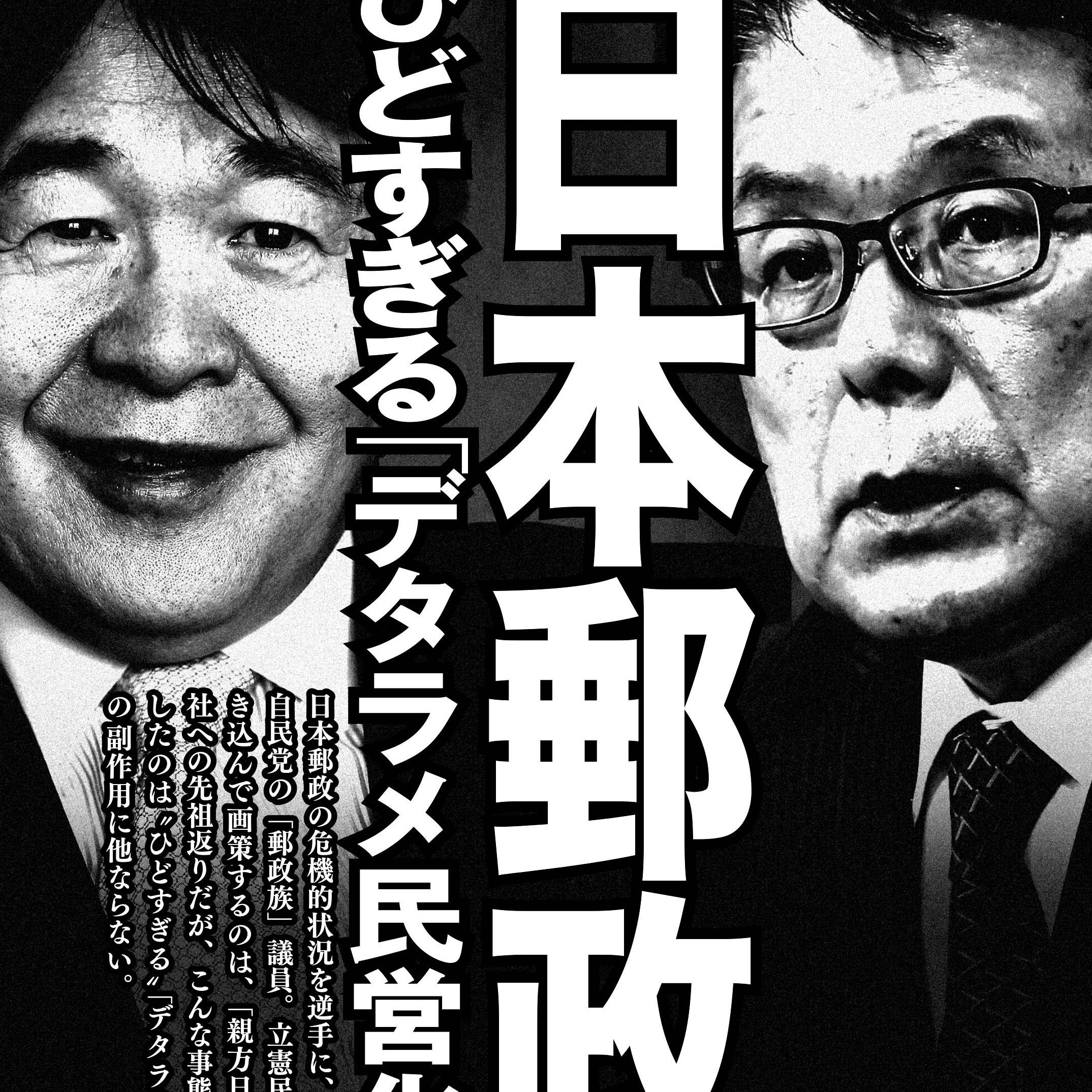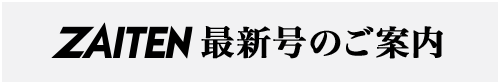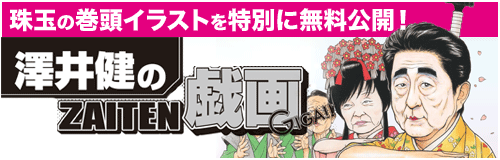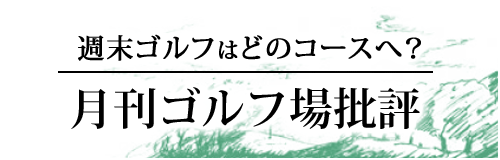ZAITEN2021年10月号
住友商事、KDDI、ENEOS、キリンHD……
日本企業「ミャンマー軍政」加担の言い分
カテゴリ:企業・経済
 ENEOS本社前での抗議活動
ENEOS本社前での抗議活動
2月にクーデターが発生したミャンマーで事態打開への見通しが立たない中、現地でビジネスを展開する日本企業の事業リスクが顕在化している。現地の合弁相手などが市民の弾圧を続ける国軍に連なる例が多く、事業継続に批判が集まるだけでなく、政情不安で事業そのものの先行きにも不透明感が漂う。一方、長く投資を続けてきた事業からの撤退も容易ではない。去るも地獄、残るも地獄。そんな様相を呈している。
キリン「国軍企業」と合弁も"事業撤退"には否定的
「減損は非常に残念であり、重く受け止めたい」。ビール大手、キリンホールディングスが8月10日に開いた2021年1~6月期の決算説明会で、社長の磯崎功典は唇を噛みしめた。同社は同年4〜6月期に214億円の減損損失を計上し、21年12月期の純利益の見通しを従来予想の1030億円から865億円に下方修正した。 この要因こそがミャンマーである。キリンは「新型コロナウイルスの感染再拡大による販売減少とカントリーリスクの上昇」を減損の理由に挙げる。 キリンは15年に最大手のミャンマー・ブルワリーに約700億円を投じ、市場に参入した。その後に買収した競合と合わせ、市場シェアの9割を握った。ビール事業はシェアが高いほど大きな利益を生みやすい。「ビールの味もいいし、設備も悪くない。素晴らしい買い物をした」。あるキリン幹部は買収直後、満足げな様子でそう周囲に語っていたという。
キリン幹部が胸を張ったのには理由がある。実は、過去のキリンにとって海外事業は鬼門中の鬼門。最大の悪夢が11年に約3000億円を投じて参入したブラジル事業だ。日本国内のビール市場が縮小を続ける中、前社長の三宅占二が次の成長の柱として白羽の矢を立てたのが当時、有力新興国BRICsの一角で、急成長を続けていたブラジルだった。 「こんなに良い案件はない」と三宅が誇った買収だったが、間もなくブラジル経済は急失速。同国事業は激しい価格競争に巻き込まれ、市場シェアも下降を続けた。15年12月期には1140億円もの巨額減損に踏み切り、1949年の上場以来初の最終赤字に転落。この〝お荷物〟事業は結局、17年に770億円で売却された。わずか6年で「損切り」を迫られ、高い授業料を支払った。
ブラジルを教訓にキリンが打ち出したのがアジア回帰。日本から地理的に近く、市場成長が期待できるアジアを重点市場と定めた。その橋頭保とも言えるのが、まさにミャンマーだった。当初、利益貢献は限られたが、海外事業の柱として順調に成長するミャンマー事業は「希望の星」でもあった。 だが、2月に発生したクーデターは、そんなキリンの想いをあっけなく打ち砕いた。キリンのミャンマー事業は、ビール製造や金融業などを手掛ける国軍系の複合企業ミャンマー・エコノミック・ホールディングス(MEHL)と合弁で手掛ける。この軍とのつながりが最大の逆風となった。
クーデターからわずか数日後、キリンはMEHLとの合弁を解消する方針を打ち出した。しかし、MEHLとのつながりを背景に市民の大規模な不買運動が発生し、飲食店や小売店でも商品の取り扱いが急減。現地関係者によると、「代わりに隣国のタイのビールや欧州系のビールが店頭で目立つようになった」という。利益を生み出す圧倒的なシェアは急速に低下しているもようだ。 だが、そんな状況でもキリンは事業撤退には否定的だ。社長の磯崎は「ミャンマー事業を継続したいという考えに変わりはない」と強調する。「ブラジルに続き、ミャンマーまで落とせない」とのキリンの思惑が透ける。 合弁解消の方針を打ち出してから半年、交渉を続けてはいるが、進展はない。欧米の投資家などはキリンが合弁解消に踏み切らなければ、投資対象から除外する構えも見せる。加えて、事業環境の悪化は、今回の減損に代表されるように経営リスクに跳ね返り始めている。キリンは苦しいジレンマに陥っている。
国軍リスクに晒される「日の丸プロジェクト」
11年に民政移管されたミャンマーに進出した日本企業は約400社に上る。キリンと同じように「国軍リスク」を抱える日本企業は少なくない。 最大都市のヤンゴン中心部の大型都市開発プロジェクト「Yコンプレックス」。このプロジェクトは、東京建物やフジタ、官民ファンドの海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN)が現地企業と合弁で18年から開発を進める。今年、開業予定で併設されるホテルはホテルオークラが運営する計画だった。 総事業費は約370億円で、うち8割を日本の公的機関や民間による投資が充てられる。18年には国際協力銀行(JBIC)が、三井住友銀行やみずほ銀行とともに約160億円の協調融資を実行する契約を結んだ。
だが、この官民を挙げた「日の丸プロジェクト」で、国軍とのつながりが明らかになった。このプロジェクトの用地は、かつての軍事博物館の跡地で国軍が所有している。この土地の賃貸契約が国軍との間で結ばれ、賃貸料が合弁相手の現地企業を通じて、国軍の兵站局に払い込まれていた。賃貸代は年210万ドル(約2億3000万円)に上るとされる。 そもそもミャンマーの国防予算は監査の対象外で、資金の流れは不透明だ。これまで支払った賃貸料の流れや使途も明らかにはなっていない。日本の官民による投資が国軍に流れている現状について、NGOなどの人権団体は「国軍との経済的関係を断つべき。できない場合は事業から撤退すべき」と開発企業やJBICなどに迫っている。
インフラ事業でも同じリスクが存在する。ヤンゴン近郊には、大手商社のほか、国際協力機構(JICA)が出資・開発した「ティワラ経済特区」がある。ミャンマーにおける日本の官民プロジェクトの象徴だ。19年からその経済特区とヤンゴンを結ぶODA事業「バゴー橋建設事業」が進む。横河ブリッジと三井住友建設が280億円で共同受注した。
問題は、キリンと合弁するMEHLと同じ国軍系で、通信事業や製造業などを手掛けるミャンマー経済公社(MEC)がその下請けに入っていることだ。この事業に関わるエンジニアの内部告発を3月に報じた現地メディアによると、「MECは橋の3分の2の鉄骨を供給し、莫大な利益をあげる計画」だという。
このMECとMEHLという2つの国軍系企業は傘下に100社以上の関連会社を抱える。2月のクーデターを受け、両社ともに米国の制裁対象に指定された。日本企業がクーデター前と同じように、こうした企業と取引を続けることにはリスクを伴う。
......続きは「ZAITEN」2021年10月号で。