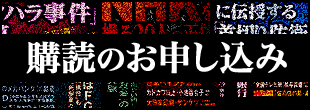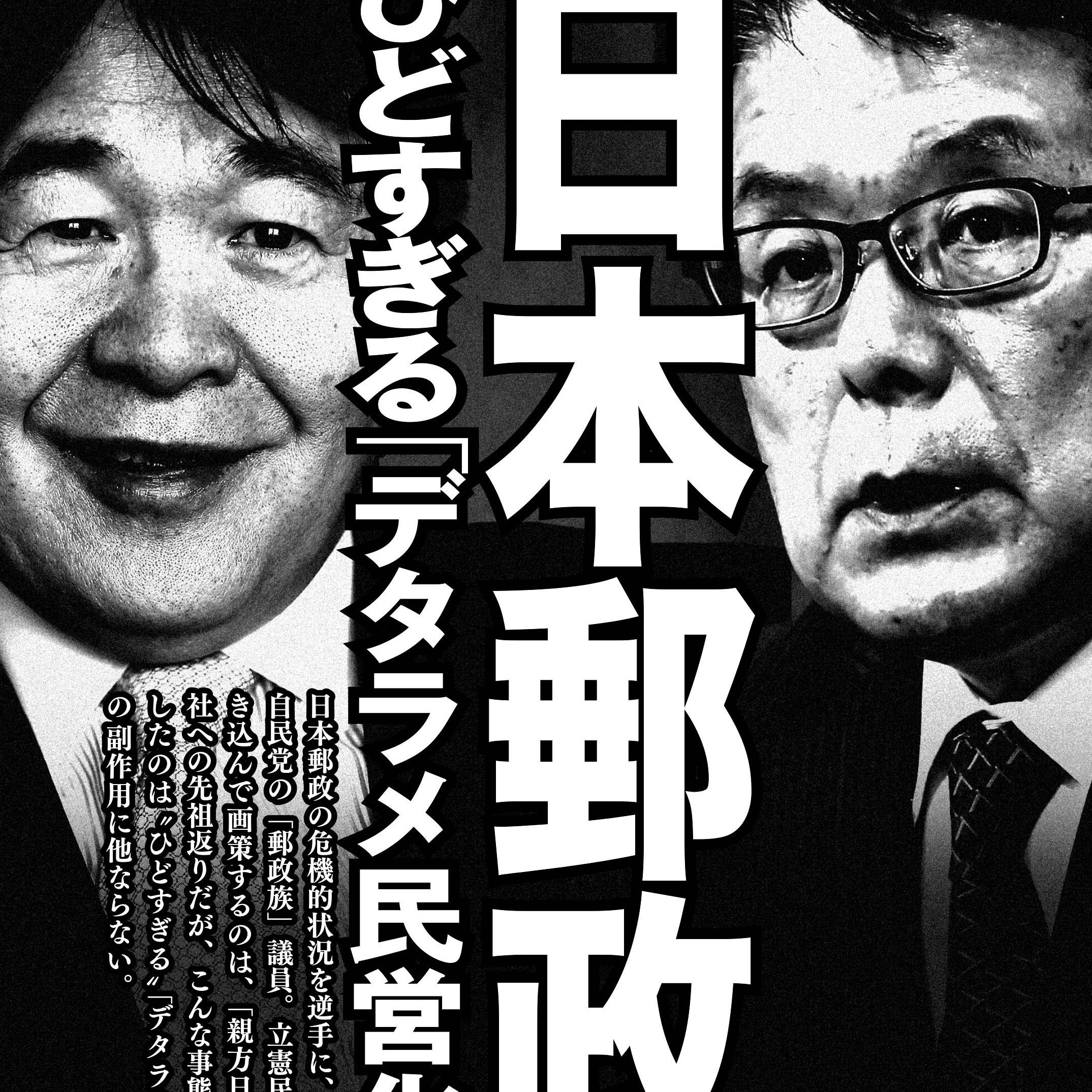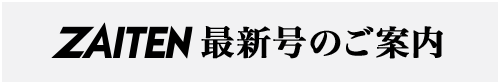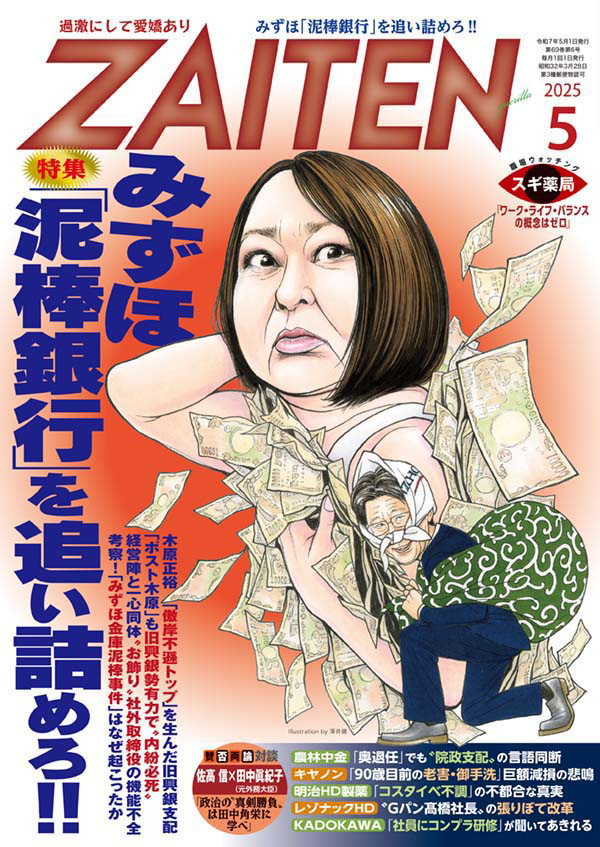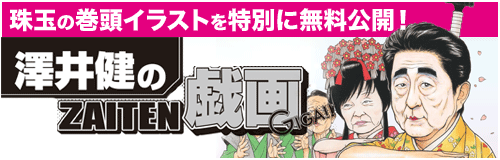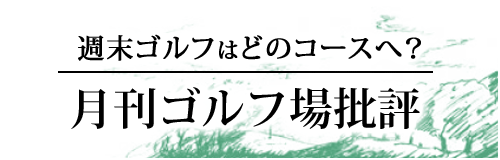ZAITEN2022年06月号
大学に巣くう財界人・官僚・マスコミ関係者
【特集】国立大学を操る「経営協議会」学外委員リスト
カテゴリ:企業・経済
国立大学が2004年に法人化されたことで、最も大きく変わったのがガバナンス体制だ。
法人化以前は、教授会に選出された評議員や学部長で構成された評議会が最高意思決定機関で、学内の投票の結果に基づいて学長を指名していたほか、教授会の意見をもとに教育・研究など大学運営の重要事項を決めていた。
それが、小泉純一郎政権下で行われた法人化によって、学外者の意見が強く反映されるようになった。その際、新たに設置されたのが「経営協議会」だ。経営協議会は半数を学外者が占め、その他は学長や理事などの大学幹部が構成員になる。議長は学長であり、学長が委員を選出する。従来の評議会は教育研究評議会と名称を変えて権限が縮小された。
経営協議会は次のような事項を審理すると定められている。
①中期目標についての意見、中期計画及び年度計画のうち経営に関する事項
②会計規程、役員報酬基準、職員給与基準、その他経営に関する重要な規則の制定・改廃
③予算の編成・執行、決算
④経営面での自己評価 ⑤その他国立大学法人の経営に関する重要事項
このように、大学経営にとって重要な役割を担っているのが分かる。しかし、各大学の学外委員のリストを見ると、その目的に沿った人選なのか首を傾げざるを得ない面々がいる。また、財界人の名誉職や、元官僚の天下り先になっている面も感じられる。
また、現在の最高意思決定機関である学長選考・監察会議のメンバーも、教育研究評議会の学内委員、文部科学大臣が任命する監事とともに、経営協議会の学外委員から選ばれる。ただ、学外委員は学長が選ぶので、実質的には学長の息がかかった人物が選考・監察会議のメンバーになる可能性が高い。結果、学長と経営協議会の委員が〝持ちつ持たれつ〟の関係になり、大学を私物化する傾向が近年顕著になっている例もある。
......続きはZAITEN6月号で。