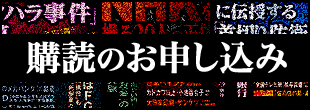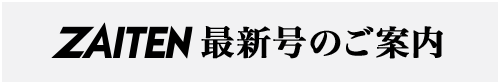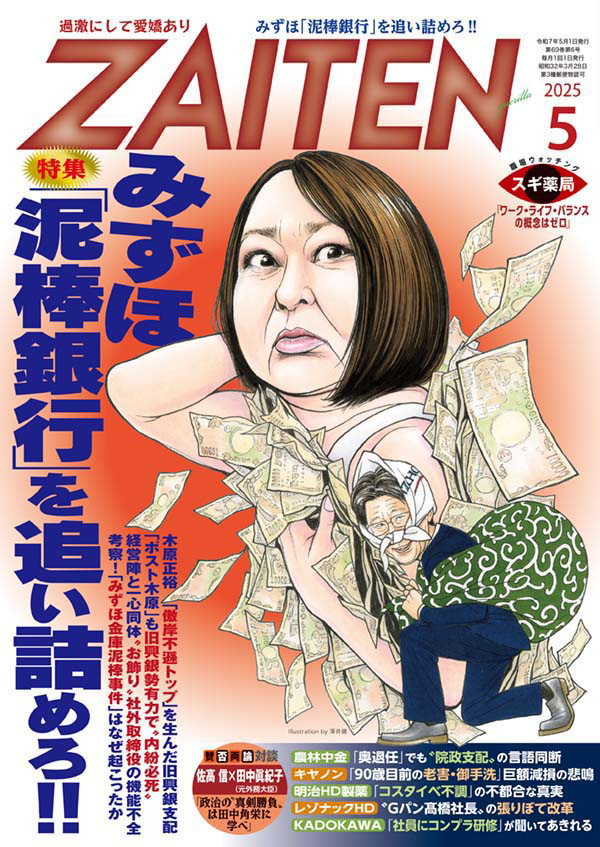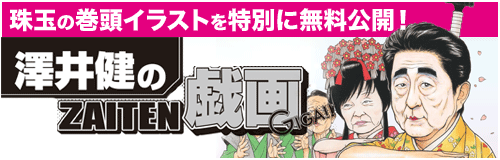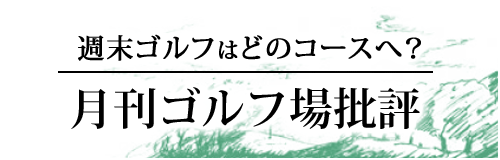ZAITEN2024年07月号
パワハラ放置の佐藤康博元会長を提訴へ
【全文掲載】みずほ敗訴「自宅待機5年裁判」
カテゴリ:TOP_free
※ZAITEN2024年7月号(6月1日発売)で掲載した〈みずほ敗訴「自宅待機5年裁判」〉を全文公開します。
※文中肩書は2024年6月当時です。
みずほ銀行「元行員への自宅待機命令」に〝違法〟判決
東京地裁で判決が言い渡されたのは4月24日。法廷ではみずほ側が欠席するなか、裁判長が主文を読み上げた。
「このような長期間の自宅待機命令は、通常想定し難い異常な事態というべきである。被告(みずほ銀)は、原告に対し、330万円及びこれに対する令和3年10月8日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。原告のその余の請求をいずれも棄却する」
原告と弁護団は、判決からおよそ2時間後に会見に応じた。原告代理人の笹山尚人弁護士は、この判決の意義を次のように表現した。
「(判決は)みずほ銀行の対応は不誠実であると言わざるを得ないと判断をしております。そして、本件の自宅待機命令については、最終的には社会通念上許容される限度を超えた違法な退職勧奨と、不法行為が成立すると判断し、原告が著しい精神障害を負う精神的苦痛を受けたことを踏まえて、賠償を命じた内容でした。裁判所が違法な自宅待機の期間であると認めたのは4年半になります。このように長期間の自宅待機が違法であると命令した事例は、私は見たことがありません。メガバンクでこういったことが行われるのは許されないと判断したことは、社会に対する影響として極めて大きいと考えており、評価できると考えています」
この裁判は、みずほ銀の元行員の男性が、みずほ銀人事部による執拗な退職強要や、5年に及ぶ自宅待機の末に懲戒解雇されたとして、みずほ銀に対して「解雇は無効」として労働契約上の権利を有する地位にあることの確認や、慰謝料1500万円を含む約3300万円の損害賠償と未払い賃金の支払いを求めたもの。2021年9月の提訴から2年半あまりで出た判決は、男性の一部勝訴と言える内容だった。前述の通り、裁判所はみずほ銀による自宅待機命令が違法であると判断し、330万円の賠償をみずほ銀に命じた。
みずほ銀側は裁判で、男性に「退職勧奨」をしたのは2度だけであり、長期間の自宅待機命令は「法的な問題性がない」と主張していた。その主張を裁判所が「このような長期間の自宅待機命令は、通常想定し難い異常な事態というべきである」と退け、違法と見なしたことについて男性は「大きな意味があった」と述べた。
「異常な自宅待機には正当な理由もなく、私がこの8年間、働きたくても働けなかった状況を踏まえると、この自宅待機を違法とした司法の判断は大きな意味があったのかなと思います」
一方で、男性が求めていた解雇の無効については、懲戒解雇を有効と判断して、地位確認やそれに伴う賃金請求を認めなかった。
自宅待機開始から約8年...
本誌は自宅待機命令が出ていた最中の21年5月号から、男性の悲痛な叫びを伝えてきた。既報の原稿の一部は本誌のホームページに掲載している。みずほ銀から男性に対して異常とも言える退職強要と長期の自宅待機命令が行われた経緯を、改めて振り返りたい。
男性は地方銀行からみずほ銀に07年にキャリア即戦力採用枠で採用され入社した。タブレット端末を活用したコンサルティングなどで優秀な成績を上げて、社内の模範となる取り組みを表彰する「みずほ銀行アウォード賞」を合計4回受賞。当時みずほフィナンシャルグループ(FG)社長だった佐藤康博から2度、直接激励を受けた。2回目には肩を組んで記念撮影し、「活躍を期待している。また頑張ってくれ」と言葉をかけられていた。
このように社内では「模範社員」として評価されていたはずの男性は、突然退職強要を受けることになる。きっかけになったと男性が考えているのは、京都支店に勤務していた14年12月に起きた出来事だ。当時、みずほ銀京都支店と旧みずほコーポレート銀行(CB)が合併により同じフロアにあった。CBの京都営業部長だった須見則夫が、営業時間中に来店客から見える場所で足を組みながら新聞を読んでいたことに対して、職場や客から苦情が続いていた。
支店の顧客満足度の向上を目指すCS担当の責任者だった男性は、上司と面談した上で、須見に顧客の前でそのような態度をなるべく取らないようにお願いするメールを送った。須見は旧日本興業銀行出身(88年入行)で、のちにFG常務執行役員を経て、現在はみずほリース常務執行役員を務める人物。このメールが須見の逆鱗に触れたと行内でささやかれると、突然、東京人事部による「臨店」が支店に入り、男性に問題行動がないかどうかの身辺調査が始まった。臨店調査終了後、男性は
須見と廊下ですれ違った際、須見から『覚えておけよ』と小声で言われた。
すると、翌15年3月以降、男性は東京人事部に度々呼び出され、16年4月には突然、自宅待機が命じられた。人事部からの退職強要は11回におよび、男性が納得できるような正当な理由は明かされず、仕事も一切与えられなかった。
自宅待機が1000日を目前とした18年12月、男性は内部通報に踏み切る。しかし、みずほ銀は内部で定められているコンプライアンス部による対応をせず、退職強要などのハラスメントを実行してきた人事部が接触を試みてきたことに男性は戦慄する。男性は繰り返しコンプライアンス部による適切な対応を求めるとともに、内部通報を行っていたが、聞き入れられなかった。その後、懲戒処分を乱発されて、21年5月、大規模システム障害の大混乱の最中に懲戒解雇された。これが、男性がみずほ銀から長年受けてきた仕打ちの概要である。
和解提案を拒否したみずほ
退職強要と自宅待機命令についてみずほ銀に非があることは、審理の過程でも明らかだった。それは裁判所が、男性が求める復職を前提とした和解を繰り返しみずほ銀に対して提案していたからだ。
最初に提案したのは22年8月。復職の検討を打診したところ、みずほ側は取締役会で正式に拒否した。2回目の提案は同年9月。復職を再検討することに加えて、再発防止策の提示とコンプライアンス統括部の対応、それに被告への誠意ある謝罪を検討する打診するものだった。この和解案に対して、みずほ銀が同年10月に回答したのは、秘密保持契約前提の上で2000万円の解決金を支払うこと、自宅待機が長期化したことについて「遺憾の意」を表明すること、それに公益通報者保護関連法を厳守することだった。秘密保持契約を結ぶことで、和解内容を口外禁止にして報道されないようにしたかった意図が透けて見える。男性側は受け入れられず、2回目の和解協議もまとまらなかった。
3回目の和解提案は、「復職を再検討し、原告の名誉回復のため、懲戒解雇を撤回して社員として再発防止策や正式な謝罪を行うこと」と、男性を会社都合による早期退職扱いにすることだった。裁判所が何度も男性の復職を提案したことを、男性の代理人である中川勝之弁護士も「通常の解雇事件に比べると異例といえる対応」と評価した。しかし、みずほ銀側はこの和解提案も拒否して、判決で違法の認定を受けたのだ。
男性とみずほ銀双方が控訴
一方で判決では、みずほ銀による懲戒解雇を有効だと判断して、男性の地位確認と賃金請求を認めなかった。男性はみずほ
銀が出社命令を出し始めた20 年10月以降、同年6月に施行された労働施策総合推進法、通称パワハラ防止法に沿った対応な
どを求めるとともに、体調も悪化していたことなどから出社を拒否してきた。それに対してみずほ銀が男性に懲戒処分を出
し、最終的に解雇したことについては、「男性が出社しなかったことについて正当な理由があるとはいえない」などとして、
懲戒解雇は有効だと判断した。
また、自宅待機命令が、男性が須見に送ったメールに対する報復だとは認定しなかった。理由を判決文では次のように説明した。
〈内容については正当な部分を含むとしても、須見部長への伝え方としては、たとえば、自身の指揮命令系統上で須見部長と同格の上司に対し相談し、当該上司から須見部長に対し伝えてもらうなどの対応をとるべきだったといえるから、これ自体原告の問題性を表すエピソードであるといえるし、被告から本件メールの送信を問題視されてもやむを得ない〉
しかし、メール送信の件がなければ、男性に対する退職強要や自宅待機命令は起きていなかったのではないだろうかと疑問も残る。
判決後、男性はすぐに控訴する意思を明らかにした。
「判決では20年10月から21年5月の懲戒解雇に至るまでの半年あまりを、違法な自宅待期期間とは認めませんでした。しかし、この間に起きたみずほ銀による処分の乱発について、判決では十分な検証がなされていません。また、みずほ銀がパワハラ防止法に沿った適切な対応をしなかったことについて触れられていないことは、非常に残念で仕方がありません。この
裁判の審議に対する疑問も含め、代理人弁護士に控訴することをお願いしました」
では、みずほ銀は裁判所からの和解提案を蹴った上で違法と認定されたことを、どのように受け止めているのか。判決についての見解などを質したところ、広報部は次のように明言を避けた。
「係争中の事案につき、回答は差し控えさせていただきます。本訴訟における当方の認識は、引き続き控訴審において主張してまいります」
佐藤康博元会長を提訴へ
裁判は今後、控訴審で争われるものの、前述の通り男性は今回の判決がパワハラ防止法に触れていなかったことに大きな疑問を感じている。
パワハラ防止法は、職場におけるパワハラ防止対策を事業主に義務付ける法律で、20年6月1日から、大企業を対象に義務化されている。さらに22年4月1日からは、中小企業に対しても義務化された。職員から職場におけるパワハラ相談を受けた場合、速やかに被害者に対する配慮のための措置を取ることや、事実関係の確認、それに行為者に対する罰則措置や再発防止策を講じることなどが、事業主の義務として明確化された。同時に職員が相談を行ったことで、解雇を含む不利益な取扱いを
することも禁止されている。
法律ができた背景には、企業によるパワハラが後を絶たないことがある。厚生労働省が20年に実施した「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、過去3年以内にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した人は31・4%と、約3人に1人と高い割合を示した。これだけ「パワハラを受けた」と回答した割合が多いにもかかわらず顕在化しにくいのは、泣き寝入りしている人が多いからだと推察される。それが組織的に行われるパワハラであればなおさらだろう。
男性がみずほ銀から受けた自宅待機命令は人事部から受けたもので、個人的なパワハラではなく、組織的なパワハラであることは明らかだ。だからこそ、男性は自宅待機命令が続く中でパワハラ通報を始めた。パワハラ防止法が施行されてからは、自宅待機命令を受けた当時FG社長だった佐藤康博や、社外取締役らに直接手紙を書くなどして、パワハラ防止法に沿った適切な対応をするように求めてきた。にもかかわらず、男性が求める対応がなされないばかりか、懲戒処分が乱発され懲戒解雇に追い込まれてしまった。
一方で、自宅待機命令が出された当時の人事担当者らは出世し、のちにFG人事事担当取締役などの要職に出世した人物もいる。この経緯から見ても、違法行為は組織ぐるみで行われたもので、その責任は経営トップにあると言えるだろう。
男性は一審判決でみずほ銀が行った退職強要や自宅待機命令が違法と認定されたことを受けて、新たな訴訟を起こすことを決めた。相手はこの問題の最中にFGの社長や会長を歴任し、現在はFG特別顧問と、日本経済団体連合会副会長の職にある佐藤だ。パワハラ防止法に沿った適切な対応を求めたのにもかかわらず、事業主としての義務を果たさなかったとして、佐藤を相手取り損害賠償を求めていく方針だ。本稿の執筆時点では5月下旬に提訴する予定にしている。男性は現在の思いをこう
吐露する。
「私は行内で表彰された祝賀会や、講師として参加した行内の講演会などで、3回佐藤氏と会ったことがあります。2回目に会った際、佐藤氏は私の肩に手を回して役員の前で激励するなど、私が模範行員として活躍していたことを知っていました。にもかかわらず、佐藤氏は異常な自宅待機の実態を知りながら、パワハラ防止法に沿った対応をしませんでした。公平な事実確認や、適切な措置をしてくれていれば、この異常な自宅待機は早期に解決していたと思います。私が自宅待機命令を受けていた5年間を通して、みずほの役員として在任していたのは佐藤氏ただ1人です。その責任は重いと考えています」
男性が懲戒解雇された21年5月は、同年2月から9月にかけて、みずほ銀に大規模システム障害が発生した時期と重なっている。システム障害はみずほ銀とFGに対して金融庁が業務改善命令を出す事態となり、企業風土やガバナンスに問題があるとの指摘もなされた。その企業体質と、「通常想定し難い異常な事態」と一審判決で糾弾された自宅待機命令や退職強要をみずほ銀が引き起こしたことは、無関係とはいえないだろう。
一審判決が出た今、みずほ銀は少なくともパワハラについて男性に謝罪すること、関係者に厳正な処分を行い、再発防止策を示すことくらいは、メガバンクに相応しいガバナンスを取り戻すために必須であろう。 (敬称略)